
CBDCの実験行う先進国が急増
国際決済銀行(BIS)が中央銀行デジタル通貨(CBDC)についての調査結果を6月14日発表した。
調査は2023年に行われたもので、86の中央銀行が参加。うち28行が先進国(AEs)で、58行が新興国・途上国(EMDEs)であった。
調査に参加した中央銀行の管轄区域は、世界人口の81%、経済生産の94%を占めるとのこと。また回答した中央銀行の94%がCBDCに取り組んでいるという。
具体的には約30%の中央銀行がリテール型CBDCのみに焦点を当てており、2%がホールセールCBDCにのみ取り組んでいるとのこと。また、回答者の54%が概念実証実験を行っており、31%がパイロット(試験運用)を実施しているとのことだ。
特に先進国でのCBDCの実験やパイロットが急増しており、概念実証は81%、パイロットは33%実施されている。なお2022年はそれぞれ60%、10パーセントであるため、どちらも増加した結果となった。
また新興国・途上国では、概念実証は39%、パイロットは19%実施された。昨年はそれぞれ37%、16%であったため微増した結果となった。
相互運用性を最重要視
またBISによれば、多くの中央銀行がホールセールCBDCについて相互運用性を最重要視しているという。
調査対象となった3行に2行の中央銀行が国内の他の決済システムとの相互運用性を確立する可能性があると回答。先進国で69%、新興国・途上国で58%の割合であった。
また国境を越えた他の決済システムとの相互運用可能なホールセールCBDCについては新興国・途上国の方が多く検討している。
他の法域のCBDCと相互運用可能なホールセールCBDCを検討するとしたのは、先進国で31%、新興国・途上国で53%、その他の国際的な決済システムとの相互運用を検討するとしたのが先進国で23%、新興国・途上国で53%となった。
ステーブルコインの利用はまだごくわずか
またBISはステーブルコインの状況についても報告している。
回答した中央銀行の半数以上が、管轄区域内でのステーブルコインの利用はまだごくわずかであると回答したという。
回答者によると、暗号資産取引や分散型金融以外で利用されている場合は、主に送金やリテール決済のニッチグループによるものだという。また約18~25%の中央銀行が、決済目的にもよるが、ステーブルコインが決済手段としてどの程度利用されているかわからないと回答している。
日本におけるCBDCの動き
日本におけるCBDCの動きとしては、政府・日銀は1月26日、CBDCに関する連絡会議の初会合を財務省内で開催。関係府省庁がCBDCを導入した場合に生じる課題を洗い出し、今春を目途にその時点での議論を整理することで一致した。
日銀が進めるCBDCの実証実験は、昨年4月より「パイロット実験」の実施が進められ、同年7月には「CBDCフォーラム」の設置と開催が発表された。そして12月には有識者会議の取りまとめを公表していた。
なお日本においてCBDCを導入するかどうかは現時点では決定しておらず、日銀としては「今後の国民的な議論の中で決定されるべきもの」との考えである。
関連ニュース
- IMF、世界銀行、BISが初の「トークン化」協力へ=ロイター
- 2030年までに24の中央銀行がデジタル通貨を導入=BIS調査
- BISと英中銀、分散型台帳技術活用の決済システムをテスト
- 政府・日銀、CBDCの連絡会議を初開催 課題洗い出しへ
- フィリピン中銀、ホールセールCBDCの試験運用の年内終了目指す=報道
参考:BIS
images:iStocks/Wavebreakmedia
参照元:ニュース – あたらしい経済
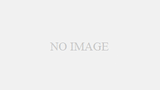
コメント