
仮想通貨の制度・規制の論点を整理
金融庁は2025年4月10日に、暗号資産(仮想通貨)に関する制度の現状と課題を整理し、規制見直しの論点をまとめたディスカッション・ペーパーを公表しました。
この資料に基づき、広く一般からの意見募集も始まっています。資料では暗号資産取引の実態と問題点がまとめられ、今後の規制見直しに向けた重要な論点が示されています。
今回の発表に先立ち、与党は2024年末の税制改正大綱で「一定の暗号資産を国民の資産形成を助ける金融商品として扱う」方針を明確に打ち出しました。これを受けて金融庁は非公開の勉強会を開催し、制度の検証を重ねてきました。
今回のペーパーには、これまでの検証結果が盛り込まれており、利用者を守りながらも技術革新を促す、バランスの取れた規制の在り方が示されています。
金融庁は意見募集の締め切り後、集まった意見を分析し、今年6月頃までに今後の規制の方向性と残された課題をまとめる予定です。
>> 暗号資産に関連する制度のあり方等の検証(ディスカッション・ペーパー本文)
>> 暗号資産に関連する制度のあり方等の検証(概要)
暗号資産制度の見直しに向け幅広く意見を募集
金融庁は今回のペーパー公表と同時に意見募集を開始し、5月10日17時まで電子メールで広く声を集めています。
金融庁が作成した今回の資料は「暗号資産市場の健全な発展」と「利用者保護」という二つの目標に向け、現行制度の課題を明らかにし、規制見直しの具体的な方向性を示す内容となっています。
ステーブルコインの規制のあり方
ペーパーによると、円やドルなどの法定通貨に価値を連動させた「ステーブルコイン」については、現時点で特別な規制強化は検討されていません。
ステーブルコインは送金や支払いの手段として期待されており、名前の通り価格が安定しているのが特徴です。日本では既に資金決済法により、発行・流通ルールが整備されており、2023年から銀行や信託会社による発行も解禁されています。
今年2月の金融審議会では、ステーブルコインの担保として日本国債以外の資産も認めるなど規制緩和が報告され、市場を活性化させる取り組みが始まっています。
金融庁は今後もステーブルコインを主に決済手段として捉え、投機性の高い暗号資産とは区別して取り扱う方針です。
ステーブルコイン運用の柔軟化
利用者資産の保護と分別管理の強化
取引所が預かる利用者の資産をどう守るかも重要な検討事項となっています。金融庁は資産の国内保管義務化や、信託を活用した管理の厳格化など、具体的な保護策について幅広く意見を募っています。
金融庁はFTXなど海外取引所の経営破綻を教訓として、取引所資産と顧客資産を厳格に区分管理し、仮に取引所が倒産しても確実に利用者の資金が返還される体制構築を目指しています。
日本では既に、利用者から預かった法定通貨を信託銀行で管理する「信託保全」が交換業者に義務付けられており、市場の健全な発展に寄与しています。
今回のディスカッション・ペーパーでも、さらなる利用者保護策として顧客暗号資産の国内保管や信託による管理強化を検討する必要性が指摘されています。
Web3や分散型金融(DeFi)に対する規制のあり方
金融庁は、革新的な技術発展を阻害せずに、Web3や分散型金融(DeFi)といった新たな金融サービスを育成するため、最適な規制のあり方について様々な立場からの意見を募集しています。特に国際的なルールとの整合性や、ユーザー保護策の具体的な方法について検討しています。
Web3やデジタルトークンを基盤とした新たな経済圏が、日本が抱える社会課題の解決や生産性の飛躍的向上につながる可能性を評価しています。
新興プロジェクトの資金調達手段として発行されるデジタル証券(いわゆるICOトークンや経営参画権を示すガバナンストークンなど)の取引が活発化すれば、革新的なビジネスの創出が加速すると期待されています。
一方で、銀行などの仲介者がいなくても自動的に動く分散型金融(DeFi)の広がりについては、将来を見据えた慎重な対応が必要とされています。
報告書では、個人が自分で管理するウォレットを使った分散型取引所(DEX)の利用が今後増える可能性にも触れ、世界的なルールづくりや技術の進展を見守る必要性を指摘しています。
Web3発展の重要性
マネーロンダリング・テロ資金供与対策(AML/CFT)の強化
金融庁は資金洗浄やテロ資金供与対策(AML/CFT)のさらなる強化に取り組んでいます。暗号資産の匿名性を悪用したマネーロンダリングのリスクへの対応策として、国際機関FATF(金融活動作業部会)が定めた「トラベルルール」の徹底について関係者の声を集めています。
金融庁は国際的な基準に沿って、暗号資産取引のトレーサビリティ(追跡可能性)向上策を推進しています。ディスカッション・ペーパーでも、FATF(金融活動作業部会)の「トラベルルール」に準拠した情報管理体制の重要性が強調されています。
日本では2022年にこのルールを国内の暗号資産取引所(交換業者)へ適用しましたが、今後はステーブルコインを含むデジタル決済手段にも対象を拡大し、より広範な取引で送金者情報の確認・通知を義務付ける方針です。
さらに金融庁は、無登録業者への対応強化や取引モニタリングの高度化など、AML/CFT分野での追加措置も検討しています。無許可で営業する海外暗号資産取引所の利用抑制策や、ミキシングサービス(資金洗浄に悪用される匿名化手法)への対処などが今後の課題として挙げられています。
トラベルルールとは
日本の暗号資産市場が抱える課題
暗号資産市場の急成長に連れて投資勧誘を装った詐欺行為も急増しており、金融庁には月平均300件を超える苦情相談が寄せられています。
一方で、国内の暗号資産交換業者の口座数は延べ1,200万を超え、預かり資産残高も5兆円を超えるなど市場規模は拡大しています。
投資経験者の約7.3%が暗号資産を保有しており、これは外国為替証拠金取引(FX)や社債を上回る水準です。
こうした状況を踏まえ、金融庁は市場の健全化に向けた規制の見直しが不可欠と判断し、今回のディスカッション・ペーパーで制度改革の必要性を提起しています。
金融庁、暗号資産のルール整備を本格化
今回のディスカッション・ペーパー公表に先立ち、2025年2月の自民党会合において金融庁は暗号資産を金融商品取引法(金商法)の規制対象に組み込む方向性を示しました。
これにより、暗号資産を発行する事業者への情報公開義務づけやインサイダー取引防止策の導入が検討されています。金融庁は2026年までに関連法改正案を国会に提出する計画で、株式市場並みの厳格な取引ルールが適用される見通しです。
こうした規制の整備が進めば、暗号資産の売買益にかかる税率も現在の最大55%の総合課税から、株式と同様の申告分離課税20%に引き下げられる可能性もあります。
暗号資産を巡る国内外の状況を踏まえつつ、必要な法改正やガイドライン整備が段階的に進められる見通しであり、利用者保護と市場育成を両立させる持続的なルール形成に注目が集まっています。
金融庁関連の注目記事はこちら
Source:金融庁発表
執筆・翻訳:BITTIMES 編集部
サムネイル:Shutterstockのライセンス許諾により使用





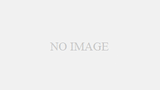
コメント