
暗号資産規制の見直しを承認
金融庁は2025年2月19日、金融審議会総会で「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」の報告書を承認しました。
この報告書では、日本国内の暗号資産(仮想通貨)市場におけるステーブルコインの運用ルールの見直しや、暗号資産交換業者の破綻時における利用者資産の保護強化、さらにトラベルルールの適用範囲拡大が示されています。
 暗号資産・電子決済手段(ステーブルコイン)概要(画像:報告資料)
暗号資産・電子決済手段(ステーブルコイン)概要(画像:報告資料)
これまで日本の暗号資産市場は、厳格な規制のもとで運営されてきましたが、市場の成長とともに新たな課題が浮上しています。特に、ステーブルコインの運用制限が流動性の阻害要因となっていた点や、暗号資産交換業者の破綻時に顧客資産が海外に流出するリスク、さらにマネーロンダリング対策の強化が求められていました。
今回の規制強化では、こうした課題に対応するために以下の4つの主要な変更が含まれています。
それぞれの詳細は以下の通りです。
ステーブルコイン運用の柔軟化
これまで、日本国内で発行されるステーブルコイン(特定信託受益権)は、資産の運用方法に厳しい制限があり、日本国債のみを担保とする仕組みが市場の流動性を制限する要因となっていた。
今回の改正では、満期や残存期間が3か月以内の日本国債や、米ドル建ての米国債、一定の定期預金を活用した運用が認められることになった。ただし、これらの資産の組入比率は50%を上限とし、安定性を確保しつつ市場流動性を高める方針が示された。
この変更により、発行者の運用自由度が拡大し、国内外の取引所や金融機関と連携したステーブルコインの利活用が促進されると見られる。また、企業間決済や個人間送金の効率化を図る。
暗号資産交換業者の破綻時における利用者保護の強化
暗号資産交換業者の破綻時における利用者保護も大きな課題として挙げられていた。これまで、日本国内の暗号資産交換業者が破綻した場合、顧客資産が海外へ流出するリスクがあり、迅速な資金返還が困難になるケースが指摘されていた。
今回の改正により、金融庁は暗号資産交換業者に対し「資産の国内保有命令」を発出できるようになる。これにより、国内で管理される暗号資産の比率が増加し、破綻時の資金返還がスムーズに行われることが期待される。
さらに、交換業者が顧客資産を適切に保護できるよう、信託を活用した資産管理の強化も検討されている。これにより、利用者資産の保全が強化され、取引所の経営状況に左右されることなく、迅速な資産返還が可能になると考えられる。
トラベルルール適用で取引の透明性向上
金融庁は暗号資産取引の透明性向上にも力を入れており、国際的な規制動向に沿ったトラベルルールの適用を拡大する方針を示している。
トラベルルールとは、暗号資産の送金時に送付人および受取人の情報を記録・管理し、不正取引やマネーロンダリング対策を強化する国際基準である。今回の改正では、ステーブルコインを含む電子決済手段にも適用が拡大され、取引業者に対して適切な監督が求められることとなる。
このルールの適用により、暗号資産取引の安全性が向上し、国際取引のリスクが低減されることが期待されている。特に、違法な資金移動の監視が強化されることで、日本の暗号資産市場の信頼性が向上し、海外投資家の参入促進にもつながる可能性がある。
新たな仲介業の創設
日本の暗号資産市場における取引の多様化と利便性向上を目的として、新たな仲介業の創設が検討されている。これにより、暗号資産交換業者と利用者の間を取り持つ新たな事業者の参入が促進され、市場の活性化が期待される。
所属制の採用
新たな仲介業は、特定の暗号資産交換業者の委託を受け、その業者のために仲介を行う「所属制」を採用する方針が示されている。これは既存の金融商品仲介業や銀行代理業と同様の制度であり、仲介業者が独自の取引を行うのではなく、登録された交換業者のもとで業務を遂行する形となる。
参入規制の緩和
仲介業者は、利用者から財産を預かることがないため、利用者資産の管理義務が発生せず、賠償リスクも限定的とされている。そのため、新たな仲介業者には厳格な財産的基礎に関する参入規制を課さない方針が示されている。所属先である暗号資産交換業者が利用者に対して責任を負うことで、安全性を確保しつつ、事業者の新規参入を促進することが狙い。
AML/CFT(マネーロンダリング・テロ資金供与対策)
新たな仲介業者が暗号資産の取引を媒介する場合、実際の取引に関するAML(アンチマネーロンダリング)/CFT(テロ資金供与対策)の義務は、暗号資産交換業者が担うことになる。そのため、仲介業者には二重にAML/CFT義務を課す必要はなく、規制の簡素化が図られている。
日本の暗号資産市場はどう変わるのか
これらの措置は、日本の暗号資産市場の安定性を高めると同時に、国際基準に沿った規制の整備を進めることで、国内外の投資家にとってより魅力的な市場環境を提供することを目的としています。
特に、取引所の破綻時の顧客保護が強化されることで、仮想通貨投資家の安心感が高まると見られています。また、新たな仲介業の創設により、より多くの事業者が仮想通貨市場に参入し、市場の競争が活性化することが期待されています。
現在、SNS上では、日本の対応の遅さを指摘する国内ユーザーの声も多く見られています。施行時期は明らかになっていないものの、ここから日本がどれだけ挽回できるのか、国内の仮想通貨市場にとって重要な転換点として注目を集めています。
金融庁関連の注目記事はこちら
Souce:金融庁発表
執筆・翻訳:BITTIMES 編集部
サムネイル:Shutterstockのライセンス許諾により使用



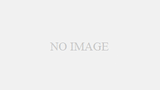
コメント