2019年、ドル/円は125円超への上昇期待! 株価は歴史的な安値圏にあり。反発は近い
■日米株は大幅に下落、2018年年初来安値を更新 週明け(12月17日)以降、日米株はともに崩れ、米政府閉鎖の可能性が伝えられる中、昨日(12月20日)大幅に続落。2018年年初来安値を更新した。
NYダウ 日足(出所:Bloomberg)
日経平均 日足(出所:Bloomberg)
米ドル/円も一気に10月安値を割り込み、にわかに本格的なリスクオフの流れを示している。
米ドル/円 日足(出所:Bloomberg)
■2019年は株安・円高局面に進むのか? 果たして来年(2019年)は、株安・円高局面へ大きく推進するだろうか。
結論から申し上げると、このような可能性は否定できないものの、確率としては低いかと思う。
ここでまず強調しなければならないのが、本格的なリスクオフの定義である。なにしろ、日米株がともに2018年年初来安値を更新しているから、リスクオフの流れがすでに始まっていることは間違いない。
したがって、これから続いていくかどうかが焦点となり、本格的なリスクオフとは、トレンドを完全に修正してしまう流れだとご理解いただきたい。
まず、米利上げサイクルに関する観測だが、2019年は4回ではなく2回しか利上げできないといった見方が強まっている。米利上げの早期打ち切り観測もあって、目先、米国株急落の解釈材料としてよく語られるが、すこし前の解釈とだいぶ違っている。
来年(2019年)、4回の利上げがあり、また、再来年(2020年)まで利上げが続くといった予測が、つい最近まで論議されていたから、「米金利の急上昇が米国株への圧力と化し、株下落の理由になる」とよく語られていた。
しかし、最近になると、一転して「2019年の米利上げの回数が少なくなり、また、早期に利上げを打ち切るから株が売られた」という解釈が圧倒的に多く聞かれるようになった。
どちらが正しいかはもはや重要ではなく、利上げ見通し自体がどちらに転んでも、株の下落の根拠になるわけなので、結局、株価次第だと思う。
要するに、仮に株が下落ではなく、上昇した場合は、米利上げ見通しの強さは米景気見通しの強さと関連させられ、株価上昇の根拠として解釈されるだろう。
そして、米利上げ見通しが弱い場合は、利上げ一服で米国株の圧迫要素がなくなることが取り上げられ、それが株高の要素として語られるだろう。どちらに転んでも後付け的な解釈が可能だと思う。
つまるところ株価次第なので、株価動向に沿った安易な解釈に流されるのではなく、自ら判断の基準を持つべきだと思う。
■目先はむしろ中段保ち合いの一環 ここで重要なコンセプトとしてまず指摘しておきたいのは、米利上げ見通しがどうであれ、来年(2019年)は米利上げがあり、また、利上げサイクルが終了していないうちは、米国株の本格的なリスクオフ、すなわちメイントレンドを完全に否定するような値動きにはなりにくいということだ。
これは過去の相場に照らして考えた「経験測」にすぎないが、相場の本質が変わらない限り、「経験測」をバカにしてはいけない。
言い換えれば、2018年は日米貿易戦争などいろいろなリスク要素が噴出し、日米株ともに10月の2018年年内高値から一転して、目先、2018年年初来安値を更新、リスクオフの流れを強め、また、大きな波乱の動きとなってきたが、米利上げサイクルがまだ完了していないうちは、これはむしろ中段保ち合いの一環と見なすことができる。
さらに、そのように位置づければ、目先の動きは行きすぎている可能性が大きい。もちろん、行きすぎとは株の売られすぎのことを指す。
■今はクリスマスセール! NYダウは年末年始に大幅反発も NYダウの週足を見ればわかるように、RSIで測れる「売られすぎ」のサインが鮮明になりつつある。
NYダウ 週足(出所:Bloomberg)
目先、2万3000ドルを割り込むまで大きく反落してきたものの、2016年10月末の1万8800ドル台や、同1月半ばの1万5800ドル台よりずいぶん高い水準にあり、対応するRSIの方は、もう2016年安値に対応する水準に切りこみ、「クリスマスセール」の様相を呈している。
目先、市場の弱気ムードは極限まで来ていると思うが、早ければ年末年始において、その反動、すなわち大幅な切り返しがあってもおかしくないとみる。
■株価は歴史的な安値圏にあり 日本株は基本的に米国株次第の側面が大きく、また「売られすぎ」のサインも米国株と同じく鮮明になりつつあるが、テクニカルよりもファンダメンタルズや市場センチメント上の割安感が目立つ。
以前のコラムでも指摘したように、日本株は今年(2018年)、最大規模の「外国人売り」(外国人投資家の売り越し、国内投資家の海外経由も含め)にさらされ、その金額はなんと12兆円にも達すると推測されるから、10月高値から大きく反落し、また、日経225先物の一時2万円の割り込みがあっても、史上最大規模の売り越しにさらされたにしては健闘している方だと思う。
【参考記事】
●記録的な外人売りの割に日経平均は大して下がっていない。米ドル/円は現状「割安」!?(2018年1月26日、陳満咲杜)
日経平均の予想PER(株価収益率)が11.5倍以下に沈み、アベノミクス相場以来最低レベルに下がっていることも大きなポイントであろう。つまるところ、テクニカルでも、ファンダメンタルズでも日本株の「割安」感が目立ってきたので、弱気一辺倒な市場心理自体が来年(2019年)の反動を暗示するものと思う。
つまり、来年(2019年)は続落よりも反動高になりやすく、目先は歴史的な安値圏ではないかとみる。米国株にしても、日本株にしても、「クリスマスセール」後、総じて回復していく可能性が高いから、来年(2019年)の相場の見通しに関して、逆に過度な弱気は不要だと思う。
■年末年始は米ドル押し目買いの好機! 同じロジックにおいて、米ドル全体や米ドル/円の見方に関しても、メインスタンスを維持していきたい。メイン基調として米ドル高は来年(2019年)もみられ、米ドル/円に至っては反動的な上値トライがあってもおかしくなかろう。
なにしろ、今年(2018年)の値幅は10円程度で、戦後の米ドル/円相場においても、最も低い変動率になるから、来年(2019年)は反動的に大幅な米ドル高か、反動的に大幅な米ドル安になりやすいかとみる。
【参考記事】
●ザイFX!で2018年を振り返ろう!(1) 米ドル一強! その時トルコショックが起きた
日本株と米ドル/円の関連性から考えて、日本株に関するロジックが間違いでなければ、来年(2019年)は米ドル安ではなく、米ドル高になりやすいだろう。
昨日(12月20日)、米政府閉鎖の可能性が伝えられ、米国株の急落とともに米ドル/円も急落してきたが、200日移動平均線の打診や3月安値を起点とした全上昇幅の38.2%反落水準の達成に伴い、下落は一時的なものに留まり、ここからの下値余地は限定的だろう。
米ドル/円 日足(出所:Bloomberg)
年末年始においては横ばいに推移する公算だが、来年(2019年)の米ドル/円は株の反発とともに上値トライ、といったシナリオが想定され、年末年始はむしろ、米ドル押し目買いの好機かと思う。
冒頭における株の話と同じように、足元では来年(2019年)…
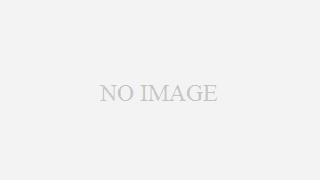 ブログ
ブログ 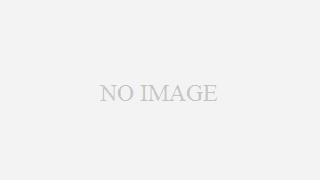 ブログ
ブログ 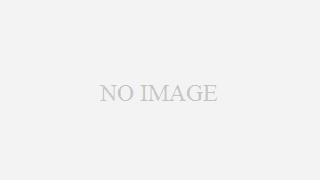 ブログ
ブログ 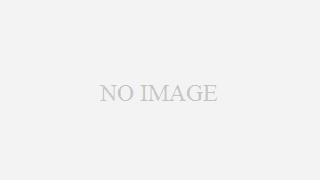 ブログ
ブログ 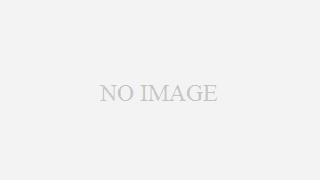 ブログ
ブログ 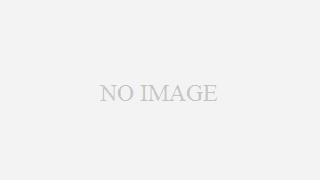 ブログ
ブログ 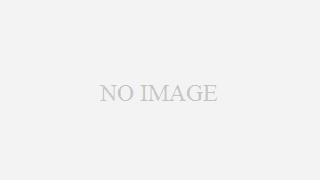 ブログ
ブログ 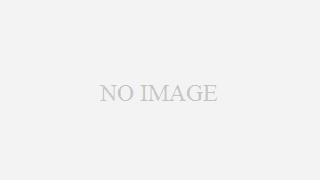 ブログ
ブログ 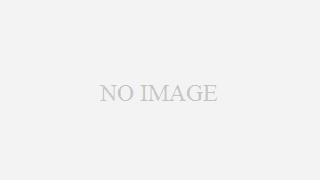 ブログ
ブログ 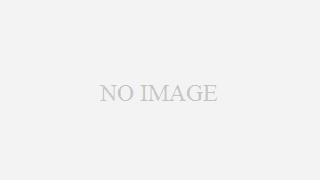 ブログ
ブログ 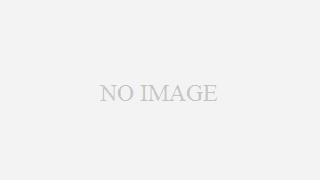 ブログ
ブログ